━━あなたは近年、コミックやスーパーヒーロー映画のジャンルから、しばらく離れたいとおっしゃっていましたね。
全体的に少し休みたいと思っていましたが、ドラマやコミック以外のプロジェクトにもっと取り組みたいと思っていたのは事実です。これらの大規模な映画シリーズに参加することは、私が計画していたことではなく、たまたまそうなっただけです。もちろん、映画『アベンジャーズ』(原題:Marvel’s The Avengers)シリーズの主要メンバーになり、並外れた象徴的なキャラクターを演じることができて、とても感謝しています。
基本的に10年以上その世界の一部となり、『ファンタスティック・フォー [超能力ユニット]』(原題:Fantastic 4)の映画 (“ジョニー”・ストーム(“Johnny” Storm)役) に出演した後は、ドラマやコメディーに出演して、さまざまなストーリーを伝えられるようになればいいなと思います。でも、私はそれらの映画での自分の仕事を常に誇りに思っています。それによって得られた大きな評価にとても感謝しています。
━━演技は常にあなたの運命だったのですか。演技が得意な分野だと常に分かっていましたか?
キャリアを始めた頃の私の態度は、素朴さと自信が混ざったものでしたが、当時は疑いもあまりありませんでした。その多くは両親から受け継いだもので、周りの人たちが私に「やってみろ」と言ってくれたおかげだと思います。たとえそれが、ほとんどの人が選ばない道であってもです。
これは間違いだと思って眠れない夜を過ごしたことはありません…。しかし、もう一度言いますが、勇気は私の手柄ではありません。両親の支援のおかげで、私は何も分からなかったのです。今振り返ってみると、あれは非常識な選択だったと思います。当時は、それがリスクであると感じさせなかったため、そのことに気付きませんでした。
全体的に、私が演技を続けることを奨励してくれたコミュニティーシアターの人々や、いつも私に自信を与えてくれた両親のサポートを受けることができたのは、とても幸運だったと感じています。
━━映画『アベンジャーズ』でキャリアが軌道に乗るまで、最後まで頑張り続けた理由は何ですか?
物事に対して健全な見方を保たなければなりません。成功が自分のアイデンティティーや幸福を定義することを許してはいけません。その2つは切り離しておかなければなりません。初めに苦労した俳優は皆、この業界がいかに予測不可能であるかを語ります。また、コールバックがもらえるかどうか、自分が期待通りの実力を発揮できるかどうかは決して分からないのです。
世の中には、才能があっても成功しない俳優がたくさんいます。とても脆い世界です。でも、演技には中毒性があります。演技にのめり込めば、本当にのめり込めば、これ以上の喜びはありません。期待に応える良い演技ができたと分かったとき、とても興奮します。それが、演技を続ける原動力なのです。
━━高校卒業後すぐに演技を始めましたね。大学進学を諦めてもらうために、両親を説得する必要がありましたか?
いいえ、実はとても簡単でした。高校3年生の夏に、両親を説得してニューヨーク市に引っ越してインターンシップをすることになりました。それが一番大変なハードルでした。夏の終わりに高校3年生を終えるために戻りましたが、オーディションのために週に1回くらいニューヨークに行っていました。
その時点では大学進学もまだ計画の一部だったのですが、その後、とても幸運なことに、パイロットの仕事に就き、それが採用されてロサンゼルスに行くことになりました。そこで、「大学進学は待てるかもしれない」と判断しました。
━━あなたが『トイ・ストーリー』(原題:Toy Story)のキャラクター、バズ・ライトイヤー(Buzz Lightyear)と『レッド・ワン』を演じたピクサー映画『バズ・ライトイヤー』(原題:Lightyear)のような家族向け映画が観客、特に子供たちにどのような影響とメッセージを与えられるかについて、どのような見解をお持ちですか?
そういった物語は、とても元気づけられるものです。そして、前向きで希望に満ちたメッセージを伝える映画が求められているのは明らかです。2時間、ただ夢中になれる映画には、常に魔法と魅力があります。私は子供の頃、それが大好きでした。
大人がリラックスして緊張をほぐす必要があるのと同じように、若者が想像力を養うことができることは重要だと思います。私たち全員がそれを必要としています。それは、映画に関して決して変わらないことの1つです。
クリス・エヴァンスによる上記のコメントは、現地時間3月2日にワシントン州シアトルのエメラルド・シティ・コミコン(Emerald City Comic Con)に出席した際に行われたものです。彼のコメントは、長さと明瞭さを考慮して要約および編集されています。
Words © Jan Janssen / Wenn
Photo © Nicky Nelson / WENN
END.

























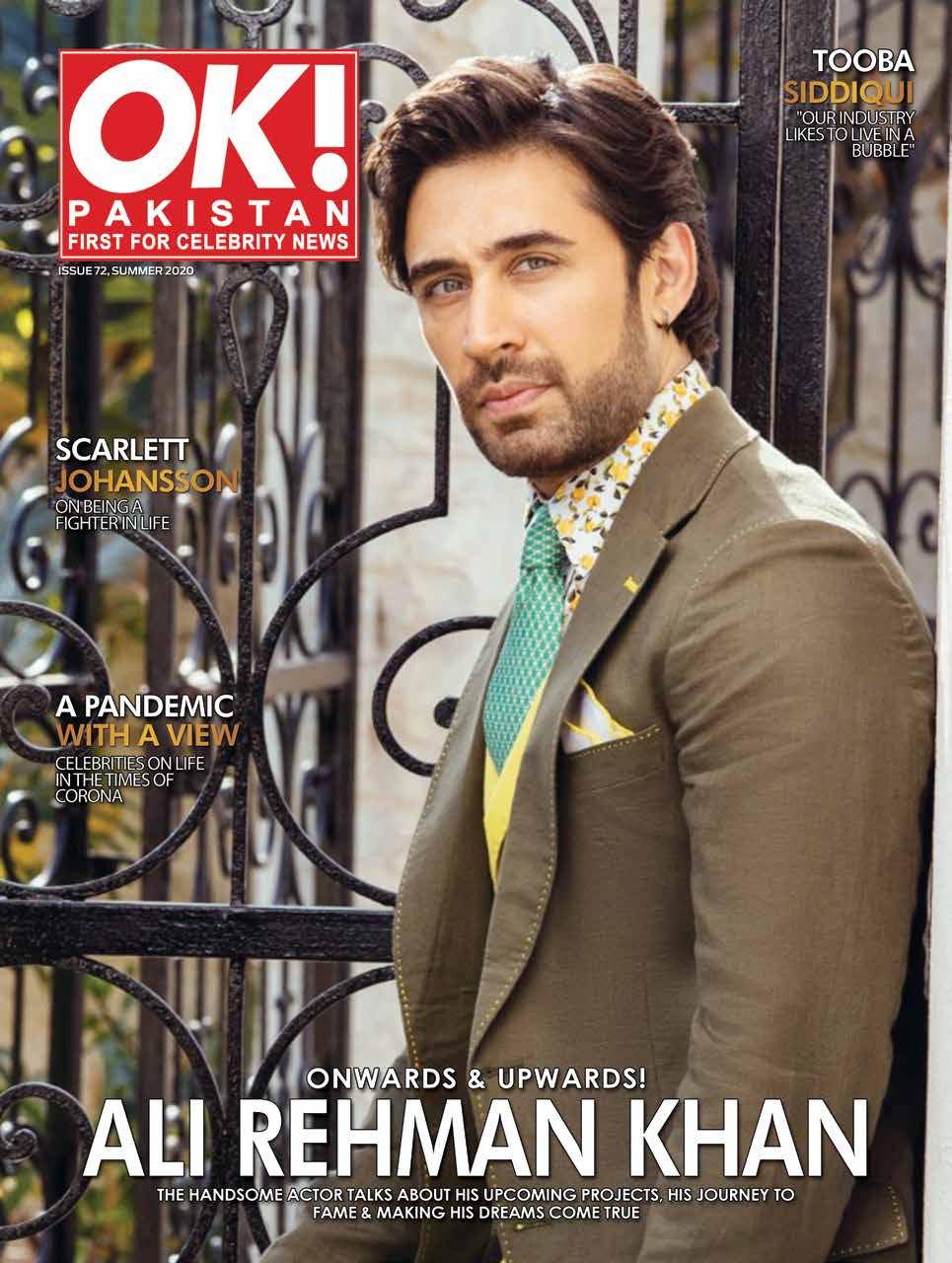




 PAGE TOP
PAGE TOP