そして、その貢献の裏には、74年という長きに渡り女王を守り、女王への献身を忠実に貫いた夫のエディンバラ公爵(エディンバラ公爵フィリップ王配(Prince Philip, Duke of Edinburgh)の力があったことは言うまでもない。そして、その最愛の伴侶であるフィリップ殿下を昨年失った女王の悲しみがどれほど大きなものだったかは想像に難くない。ちなみに殿下は100歳の誕生日を迎える数週間前にこの世を去っている。
2021年4月9日にエディンバラ公爵を失った女王の様子について王室専門家は次のように語っている。
「エディンバラ公爵の死は女王の体力、気力の衰退の始まりを意味しているようです。もちろん、女王の献身への変わらぬ決意と義務感に揺らぎはなかったものの、その深い悲しみが96歳の君主の健康に打撃を与えたことは明らかです。私たちは皆、殿下の葬儀後の女王の仕事復帰の早さに驚き、フィリップ殿下がいつも口にしていた「継続あるのみ。ですから、ただただそれを続けなさい」のマントラに従っているのだろうと思い、感動したものです。
でも女王の強い意志も、殿下を失った喪失感には叶わず、結局は肉体的そして精神的に、かなり大きな影響を及ぼしていたと思われます。強い意志を持つ女王自身は、きっと殿下との別れからくる“体力と気力の衰え”を過小評価していたのでしょう。もちろん、殿下の死は予期せぬことではなかったものの、他の国民同様、パンデミックによるロックダウンで外出や家族と会うこともできず、自宅で仕事をすることを余儀なくされる生活に不安を感じていたことも、女王の健康の悪化に拍車を掛けていたのでしょう。

現地時間2016年6月14日、アスコット競馬場で親指を立てるエリザベス女王(写真右)とエディンバラ公爵(写真左)。
昨年10月にアスコット競馬場(Ascot Racecourse)が開催された際、レースファンが口にした女王の名ゼリフ「信じるためには、まず見なければならない。」という言葉が女王の不安な思いを言い当てていると言えるのではないかと思います。そして、パンデミックの影響によるソーシャルディスタンスを考慮にいれた殿下の葬儀で見せた「セント・ジョージ礼拝堂(St George’s Chapel)に静かに座る、孤独に打ちひしがれた小さな女王の姿」には、悲痛な思いがあふれているようでした。なぜなら、私たちはそこに国家元首としての強靭な君主ではなく、脆弱な95歳の女性を垣間見て、その姿から「どのようにして女王が新しく力を手にして立ち直るのか」に不安を感じたからです。そしてその「強さと忍耐」の由来は、女王が披露した1997年の金婚式のスピーチが如実に物語っています。
「フィリップは簡単には、人の誉め言葉に乗らない人です。でも、この場を借りて私は非常に率直な私の気持ちを伝えたいと思います。彼は私の力の源であり、私の女王としての任務遂行も彼の存在、支援なしにはあり得ません。彼は決して口にはしませんが、私の家族はもとより、イギリス国民、そして連邦国家国民はフリップの影の貢献を知るべきだと思っています。」
そして女王は個人的な喪失を抱えながら多忙なスケジュールをこなし続け、パンデミックという厳しい環境の中、国民に向け改めて伝説的とも言える強さを示したのです。女王の精神がどんなに強靭であろうと、ここ数年の異常とも言える大惨事が女王を苦しめたことは言うまでもありません。そして、ハリー王子(サセックス公爵ヘンリー王子(Prince Henry, Duke of Sussex))の王室離脱による王室への非難は、特に困難なものだったと思います。女王はハリー王子の“やんちゃ”な側面を愛し、彼をとても可愛がっていましたし、国民からの人気を誇りにも思っていました。ですから王室離脱に関わる一連の出来事には非常に心を痛めていましたし、それは“アンドルー事件”(息子のアンドルー王子(ヨーク公爵アンドルー王子(Prince Andrew, Duke of York)))も同様です。」
ここ最近、歩行に支障が生じた女王は多くの王室行事に参加することを避け、公の場に姿を現すときは常に杖を携えていた。

現地時間1992年6月17日、アスコット競馬場でのエリザベス女王(写真左)とエディンバラ公爵(写真右)。
昨年10月、医療従事者から休養を勧められ、2日間に渡る北アイルランドへの旅行をキャンセルした女王は悲嘆に暮れていたようだが、その後も容態悪化のため、一晩入院し、身体検査を受けることを余儀なくされている。そして11月になると事態はさらに悪化し、背中を捻挫した女王はザ・セノタフ(The Cenotaph)での追悼日曜礼拝に出席することができなかった。
2018年の白内障手術を除けば非常に健康で、時折の風邪や咳に苦しむ程度だった女王だが、ここに来ての体調不良は周囲の医師団に一抹の不安と懸念を与えることになった。
そして2022年に入ると、女王の公式行事はめっきり減少し、その上自身が新型コロナウィルスに感染し、その回復にかなりの時間を要した女王は、もう既に“心身共に疲れ果てた”という思いに襲われていたようだ。さらに今年4月、ウィンザー城で行われた王室恒例の“イースター礼拝”にも参加しないことが発表され、5月にはチャールズ3世が女王の代理として議会の開会式の場に参加することを余儀なくされている。
しかし、幸いにも6月に行われた、歴史的な英女王陛下在位70周年「プラチナ・ジュビリー式典(The Platinum Jubilee celebrations)」のお祝いの場には何とか間に合わせ、バッキンガム宮殿のバルコニーに姿を現した女王。ほほ笑みを携え国民に向けて手を振る姿を披露していたが、その前日の祝賀会で体調の異変を感じた女王は、6月3日にセントポール大聖堂(St Paul’s Cathedral)で行われた感謝祭の礼拝への不参加を余儀なくされている。
さらに、熱心な競馬ファンでもあるにも関わらず、エプソムダウンズ競馬場で開催される3歳馬の最強決定レース「ダービーステークス」への出席も断念したという女王だが、祝賀会が開催された週末に女王は次のようなメッセージを送っている。
「全ての行事に直接出席したわけではありませんが、私の心はいつも皆さんと共にあります。今は家族の皆に支えられ、引き続きできる限りの貢献を続けていきたいと思っています。」

「英女王陛下在位70周年」を祝い、2022年6月2日~5日にかけて開催されたビッグイベント「プラチナ・ジュビリー式典(The Platinum Jubilee celebrations)」。現地時間2022年6月5日にイギリスロンドンの開催されたプラチナ・ジュビリー式典をバッキンガム宮殿のバルコニーから祝う(写真左から)現カミラ王妃(Queen Consort Camilla)、現チャールズ国王(チャールズ3世(Charles III))、エリザベス女王、ジョージ王子(Prince George)、現ウィリアム皇太子(ウェールズ公ウィリアム(William, the Prince of Wales))、シャーロット王女(Princess Charlotte)、ルイ王子(Prince Louis)、現キャサリン皇太子妃(ウェールズ公妃キャサリン(Catherine, Princess of Wales)。
高齢でやむを得ない出来事だったとはいえ、女王の死は依然として大きな衝撃を与え、国民が偉大な君主の喪失を認め、その折り合いをつけるのにはかなりの時間を要することが予想されている。
王室専門家のダンカン(Duncan)は、そうした状況について次のように述べている。
「1952年から私たち国民の元首だった女王の死は、ほとんどのイギリス国民にとって最も重要な憲法上の出来事なんです。ですから、女王の死はきっと私たちが考えている以上に様々な形で多くの国に影響を与えるのではないかと思います。それは、家族の一員を亡くした悲しみと同じことなのです。女王の死は“第二次エリザベス朝”時代の終息であり、今は我が国の歴史の分岐点とも言える時期にあるのではないかと思います。英国は、人類の歴史上、どの国よりも“豊富な知恵と経験を”持つ人物を失ったわけですから。長い治世を通して得た女王の人智が、パンデミックに苦しむ国民を結集させ、安心を与えたことから見ても、それは明白な事実だと思います。
2020年4月に行った女王のスピーチは“戦時中のイギリス国民の精神”を呼び起こし、私たちに勇気を与えてくれました。そして女王の並外れた義務の意識は、かつてないほど国民から尊敬され、愛されていたと言えます。そして、女王が君臨した君主制がチャールズ、ウィリアム、ジョージと三代に渡って続くことを確信した女王はきっと安心して息を引き取ったことでしょう。」
21歳から臣民に誓った厳粛な誓いを守った女王は今その長き栄光を携えて、ウィンザー城で安らかに眠ることになります。国民の感謝の思いと共にOK! は “神があなたを祝福し、ありがとう”と言ってくれると信じます!
Words © OK! Magazine / Leo Roberts, Rachael Bletchley
Photos © Mirrorpix
END.

























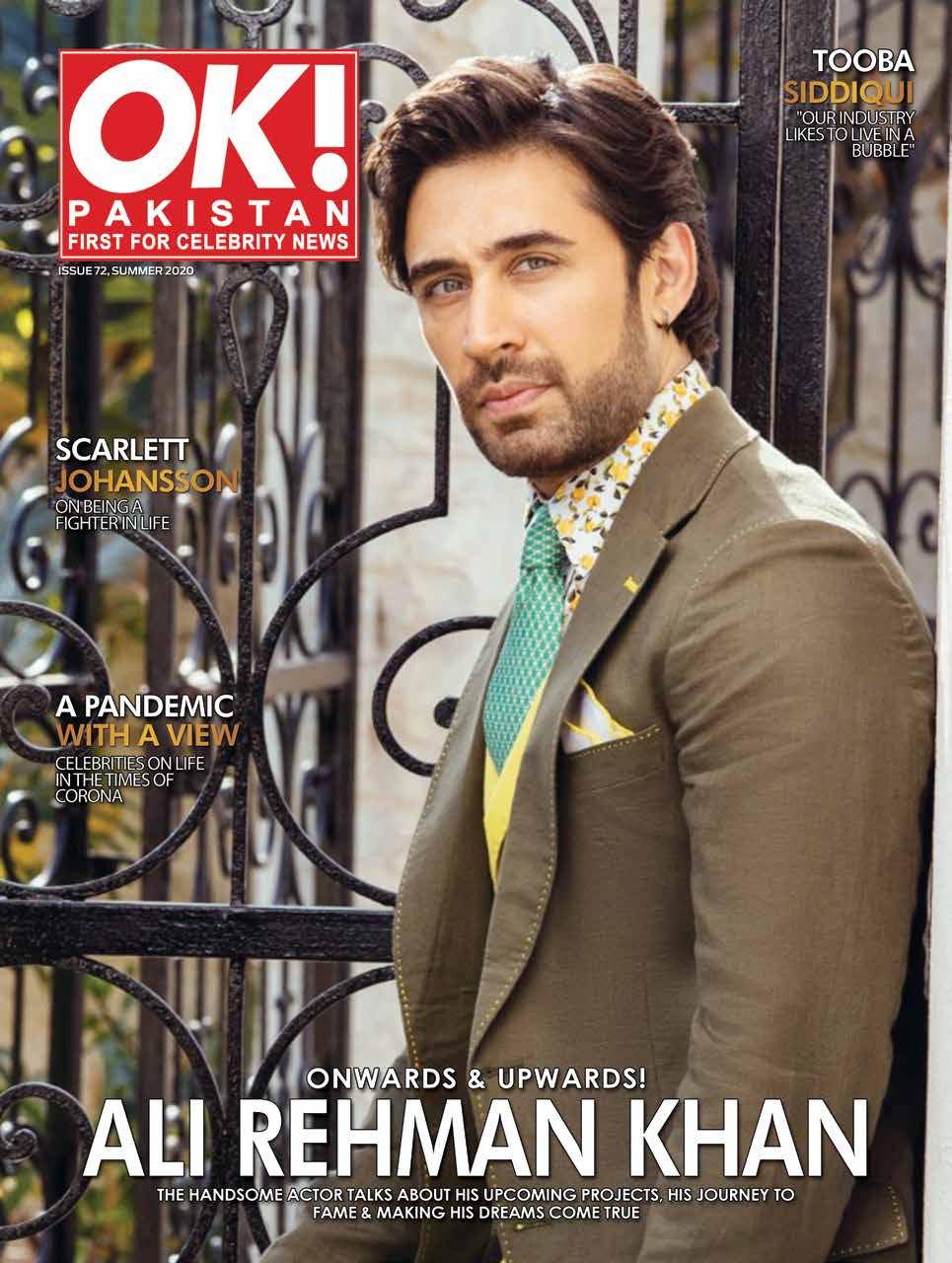




 PAGE TOP
PAGE TOP